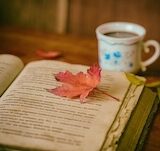10月11日土曜日の読売新聞の書評欄で、気になった本、その2。
一冊めは、「わが一期一会」 (井上靖著・毎日新聞社・絶版)
俵万智さんがセレクトした一冊で、「中2の出会い 歌人の「伏流水」」という紹介文が印象的だった。「ささやかなエピソードがこの人の筆にかかるとこんなにきれいに立ち上がるだと思った。」という一文があり、「立ち上がる」「伏流水」という表現の美しさに惹かれた。俵さんの本を読んでみたくなった。
二冊めは、「松本隆 言葉の教室」(延江浩著・ちくま文庫・880円)
「作詞活動55年記念として文庫化。なぜその詞が生まれたのかの原体験をたどっていく」との書評。文章力を磨きたい自分にぴったりの一冊に思えた。
三冊めは、「小説作法の奥義」(阿刀田 高 著・新潮文庫・693円)
書評には「そこから読み取れる奥義は、やはり真似できないものも多いが、だからこそ本質が語られているように思う」とある。真似できないけれど本質とは、その本質に迫りたいと思った。
四冊めは、「鎌倉茶藝館」(伊吹有喜著・光文社・1,980円)
評者曰く、「「まさか」の恋愛話に飢えている読者に、百点満点の満足を確約しておすすめしよう。「ページを開けば、貴女もヒロイン」の世界、ここにありだ。」
ハーレクインロマンスのような小説なのだろうか。中高年の自分でも楽しめそうだ。
今回の書評で、俵万智さんの「伏流水」という言葉がとても印象深かった。自分にとっての伏流水とは何だろう。いつか、それを見つけたい。