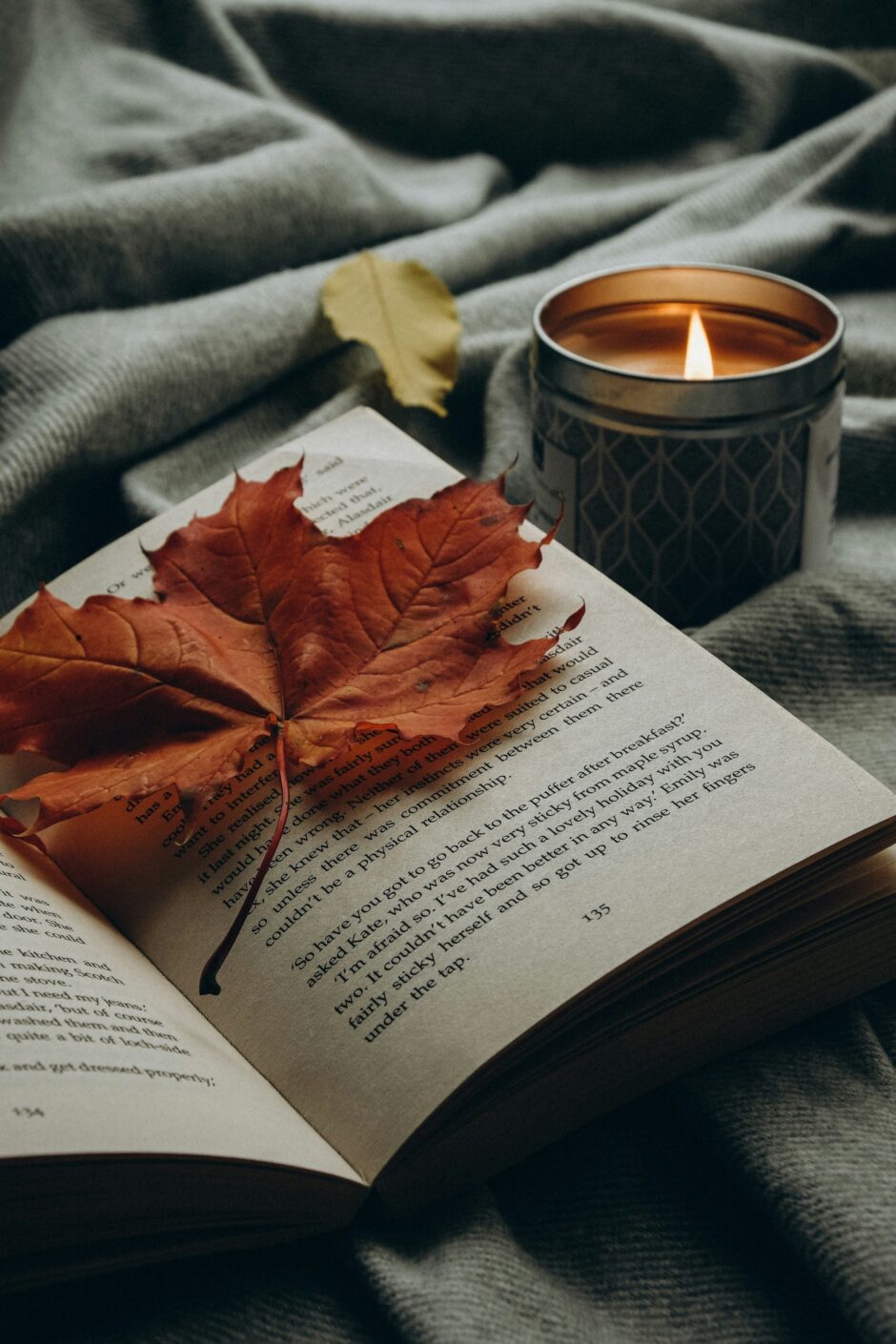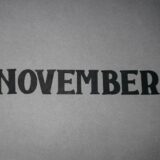2025年10月26日土曜日付読売新聞の書評欄を読んで気になった本を書き留めた。
一冊目は、野中郁次郎、勝見明著「全員経営 ハイパフォーマンスを生む現場 13のケーススタディ」(日経ビジネス人文庫・1,100円)
この本は「実践知を育成し、組織に埋め込み、圧倒的な競争力や高収益を実現している」企業のケーススタディ集だ。
書評には「強い個人が形式知を基に引っ張る経営モデルと比して、社員全員が『腑に落ちる』感覚にこそ盤石な組織力が宿る。強弱でも優劣でもなく、『全員の話』。異色のビジネス書」と書かれている。
上意下達でやらされ感が強い組織が多いなか、社員全員が「納得感を得る」ことができれば強い組織となる。どのようにして「自らの言葉として理解する」ことができるのか。今の自分や組織にどう活かすのか。本書を通じて、自分の血肉にしていきたい。
二冊目には、井手英策著「令和のファシズム論 ー極端へと逃避するこの国でー」(筑摩文庫・2,200円) を選んだ。
書評は以下の通り。
「対話と調整の機能を放棄した政治は徐々に極端へと走り、崩壊へと近づいていく。
本書が指し示すのは、より息長く、自治を育て続けることだ。
自らを、家族を、コミュニティを、社会を、理性的な検討により中庸なものとして育てる。不安に溢れた現状から真に逃れる方法は、英雄を待つことでも、極端に耽けることでもない。歴史は、そのことを明確に教えてくれる」
多様性といいながら、政治も社会も経済も、他者を受け入れる余裕がなくなっていると感じる。自分自身も、自分の尺度で他者を当てはめようとする傾向がある。自己規律と寛容、その両立を静かに考え続けていきたい。