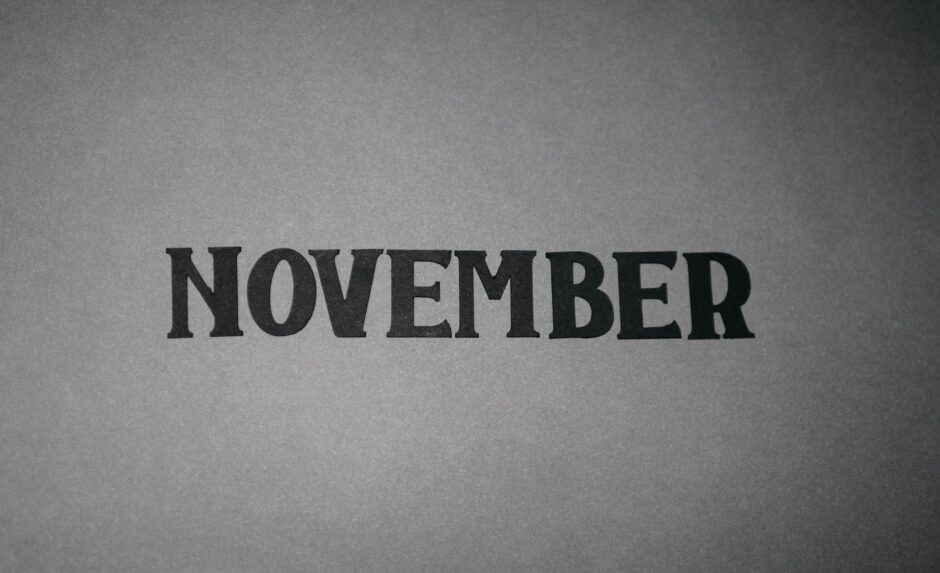2025年10月26日日曜日付読売新聞の書評欄で気になった本を書き留めた。
横田徹著「戦場で笑う――砲声響くウクライナで兵士は寿司をほおばり、老婆たちは談笑する」(朝日新聞出版・2,310円)
「戦時下のウクライナで生きるには『笑い』がなければ精神が持たないよ」と言う。
極限状態において、人は笑いを必要とするということだ、と書評にある。
戦争を身をもって経験したことがない自分としては、戦時下とはどのようなものかわからない。だが、戦っている人たちは何かの希望を持っているからこそ、戦っているのだろう。極限状態で何を感じるのか、何を希望としているのか、知りたいと思った。
2025年10月26日日曜日付産経新聞の書評欄を読んで気になった本を書き留めた。
一冊目は、佐藤信之著「日本のバス問題」(中公新書・1,375円)
ーバスを取り巻く今昔ー これからはバスを維持できない時代が来るかもしれません、との書評だ。
私も今年5月からバス通勤を始めた。通勤する中で、高齢者が多く利用していること知り、地域交通としてバスが欠かせない存在であると感じた。本書が、バス問題の改善につながる一助となることを願う。
二冊目は、「丸」編集部編「日本陸海軍 幻の軍用機」(潮書房光人新社・3,300円)
ー「未完の翼」を俯瞰ー
大戦末期の逆転に賭ける当時の技術者たちの苦労が伝わってくる、との書評。
子供の頃から、なぜか戦争ものの本が好きだ。特にドイツの戦車に惹かれる。日本の飛行機も隼、零戦、疾風、雷電といった機体に憧れる。日本の技術者がどんな飛行機をつくったのか、みてみたい。その技術が、今の日本の製造業の強さにつながっているのだろうか。